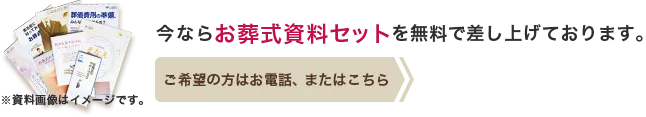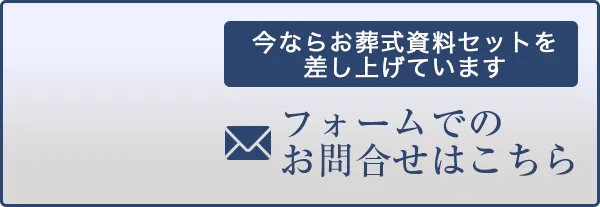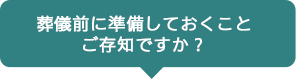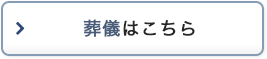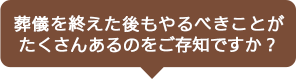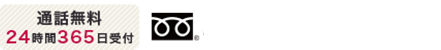沖縄
固有の文化を守る沖縄の墓と葬祭
さまざまな歴史の荒波に揉まれながらも、独自の琉球文化を守ってきた沖縄。
今回は、そんな沖縄のお墓や習わしについてご紹介します。
一族が共同で使う、大きなお墓
世界でも有数の美しいエメラルドグリーンの海、赤瓦の屋根が異国情緒を漂わせる町並み、そして人々のこころを伝える島唄。固有の風土と文化を持つ沖縄は、葬儀に関することもまた独特です。
たとえば、檀家制度のない沖縄では、お墓は寺の境内に建てる小さなものではありません。近年では、家族単位の墓もありますが、一族(門中)の意識が強いこの地方では、同族単位のお墓、門中墓が一般的です。丘陵地に広いスペースを取ってつくられるこの墓の形も、ユニーク。亀甲墓は、墓の前の庭ばかりでなく内部も広いため、戦時中は人々の避難壕にもなりました。
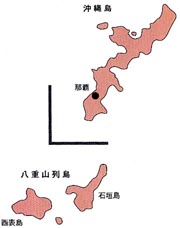
「また葬儀も、かつては沖縄ならではの方法が取られていました。埋葬と洗骨の二度の葬儀を行う「二回葬」です。
洗骨とは、埋葬した遺体が朽ちるのを待ってから、数年後に取り出して、骨を洗い清めること。洗骨された骨は木製や陶製の骨壷に移し替えて、再び墓に戻します。現代では火葬することが多いため、洗骨はほとんど行われなくなりました。」

墓の前で、賑やかに
お墓は、ときに家族や親戚が集う場にもなります。沖縄本島からさらに南に下った八重山諸島の地域では、旧暦の正月十六日、「十六日祭」という祭を行います。この日は、家族みんなで朝から墓の前に集まり、車座に座って食べたり飲んだり、ときには三線(さんしん)の音に合わせて歌ったり踊ったりするのです。
興味深いのは、その際食べるお料理。一般的に葬儀や法事の際には、肉や魚などの生き物を使わない精進料理を食べる地域が多いもの。
ところが、沖縄の島々では肉や魚の料理を供するのがよいとされ、この八重山の地域でも、かつては死者が出るとまず牛か豚を屠ったほど肉料理は大切にされているのです。
十六日祭には、この肉料理や魚料理を詰め合わせたお重をまず墓前に供え、さらにそこに居合わせる人々も供えたものと同じものをいただきます。
いま生きている人も亡き人も、同じものを食べ一緒に楽しみたい。そして、お墓のなかの人にも現世と同じ楽しさを味わってもらいたい。十六日祭には人々のそんな願いが込められているのでしょう。

訃報広告にも見られる共同体意識
親族単位で墓を持つ沖縄の人々の一族共同体意識は、実は意外なところにも反映しています。沖縄で新聞を見てまず驚くのは、沖縄タイムスや琉球新報といった地元の新聞にズラリと並ぶ訃報広告。ここでは、多くの一般家庭が地元の新聞に死亡広告のお知らせと告別式の日時を載せた広告を掲載します。しかも、目を引くのはその広告に喪主だけでなく家族や親戚故人の曾孫や配偶者、さらには海外に住んでいる親戚や友人の代表者までもが名を連ねること。訃報広告を見れば一目で故人の繋がりが分かるのです。
親から子へ、子から孫へ、そして孫から曾孫へと、代々継承していく沖縄のお墓。人々はそのお墓と共に、自分たちの家族への愛や沖縄の文化への誇りも大切に受け継いでいるのかもしれません。

韓国
儒教の教えが色濃く残る韓国の伝統的な葬儀
日本から一番近い国、韓国。
遠い昔から、文化的にも政治・経済的にも、私たちの国と密接な繋がりを持つその国には、意外と知られていない伝統的なしきたりが残っています。
そこで今回は、韓国のお葬式についてご紹介します。

親への孝行を示すために
韓国を訪れてまもなく気付くのは、人々の年長者に対するマナーの良さです。
地下鉄に乗っていて、年配の人が自分の前に立てば、さっと席を譲る。レストランでは、同じテーブルの年長者が料理に箸をつけるまで、他の人は箸をとらずに待っている。食事が終わり、席をたつのも年長者が先。日常のあらゆるシーンで、目上の人を敬う姿勢が貫かれているのです。というのも、韓国の人々の道徳観の基本には、儒教の精神が生きているため。
儒教は、もともと中国の孔子が説いた教えですが、韓国では十四世紀後半から二十世紀初期まで続いた李朝時代に国教として定められ、政治や思想に大きな影響を与えました。
信仰の自由が認められ、仏教徒やキリスト教徒が多い現在の韓国でも、実はお葬式や祭事と深く関わっているのは儒教。たとえキリスト教徒であっても、葬儀の基本部分は儒教式で行う人がいるように、儒教は宗教と言うよりも、人々の生活規範となっているのです。
「孝」を重んじる儒教では、自分を生み育ててくれた親を尊敬し、その恩に報いることがとても大切。それは同時に、自分の親の親であり、そのまた親でもある代々の祖先を崇拝し、礼を尽くすことにも繋がります。親に孝行したい、祖先を手厚く祀りたい。そのような思いは韓国の人々を、盛大な葬儀を行い立派なお墓を建てることへと向かわせるのです。


あの世からの使者を迎えて
伝統的な儒教式のお葬式には、さまざまなしきたりがあります。たとえば臨終が確認されると、遺族たちは大声で泣き、人々に葬儀の始まりを告げます。儒教では、あの世から使者が迎えに来て、亡くなった人の魂を導いてくれると考えます。そこで、まず故人の上衣を持った人が屋根に登り、北側に向かってそれを振り、あの世の使者を招くのです。家の庭には、「使者床」と呼ばれる使者のための食事や草履も用意。
また、故人があの世へ行く道のりの食料として、水に浸したお米を遺体の口に入れる習慣もあります。遺族の喪服は、正式には故人との関わりによって異なりますが、生成りの麻の韓国服に頭巾をかぶるのが基本。儒教では、両親の死は世話や誠意が及ばなかった子の罪であると考えるため、遺族は何の色にも染められていない粗末な服を着ることで、罪深さを示すのです。時には故人の思い出話に花を咲かせ、時には遺族を慰める為の歌が披露され、そして時には花札までも登場して、葬儀は延々三日間にも及びます。
その後、棺は花で美しく飾られた輿に乗せられ、墓地へ。そして、故人の名前や出身を記した旗、いわばあの世で使う戸籍謄本と共に、土中に埋葬されます。


変化する都市部のお葬式
このような自宅でのお葬式が今も地方の農村などで行われている一方で、都市部を中心に葬儀のスタイルも変化しています。実際、自宅での葬儀が難しい都会のアパートやマンション住まいの人々の間では、病院の霊安室をいわゆる葬儀場として、葬儀をとりおこなう病院葬が増加。また、身近に葬儀に詳しい親族がいないため、専門の業者に式の進行を任せるケースも多くなってきました。お墓にしても、従来は、風水に則って決めた場所に土饅頭型の小さな塚を作ってきましたが、土地不足の現代では最寄の共同墓地に埋葬されるのが一般的。さらには、年々、火葬を望む人の率も高まっています。
このように、葬儀の形は時代とともに変化し、伝統的なお葬式は次第に行われなくなりつつあります。しかし、いつまでも変わらないのは、子を愛する親のこころであり、親を思う子のこころ。そのこころが生き続ける限り、お葬式が単なる儀式となってしまう日が来ることはないでしょう。

中国
中国の葬儀改革 -古い風俗習慣にとらわれない新しい葬送へ
土に入ってこそ、安らぎが得られるとの思想のもとに、数千年来、土葬の習慣が続いてきた中国。
しかし、一九五〇年代以降、人口が密集した都市部を中心に、火葬への移行が進められてきました。
そこで、今回はそんな中国の昔と今を訪ねます。

風水で決めた墓の位置
元来、中国のお墓づくりには、二つの大きな特徴がありました。ひとつは、「風水」。風水とは大地の気の流れを読み取る技術で、日本でいう墓相や家相もその一部。中国では遺骸も含め、人の身体はすべて気の流れに影響されるもので、祖先の遺骸も風水的な観点から見たよい位置に埋葬されてこそ、富や子孫繁栄などの福が得られると考えられてきました。そのため、家族に何か凶事があると、遺骸を発掘し、新たな土地に埋葬し直すことさえ行われていたのです。
血筋と世代を重んじて
そしてもうひとつの特徴は「血筋の継承」へのこだわりとも言えるもの。一般に中国では、家系を受け継ぐのは男性のみ。一族の墓には塚が世代順に並び、ひと つの塚には夫婦が揃って葬られます。夫婦は次の世代へと血筋を受け継ぐ男子を持って初めて、自分たちもいつか祖先として祀られると感じることが出来まし た。

土葬から火葬へ
しかし、このような伝統的な中国の人々の埋葬意識にも、大きな変化を迫られる時がきました。一九五〇年代、毛沢東が火葬の導入を提唱。従来の土葬を改革し、封建的な風俗を取り除こうと呼び掛けたのです。実際、どんな広い国土を持つ中国も、都市部では人口が密集。ひとりひとりを土葬にしていたら、とても土地は足りません。
一九八〇年代には、全国で14.5%、大中都市で70~80%まで火葬が普及。さらに、これを推進させるため、人口密集地帯での火葬の義務づけ、その他の地域での土葬の制限などを盛り込んだ規定を発布しました。
遺骨は、納骨堂へ
首都・北京では、一九五八年に、八宝山革命公墓に火葬場が開設。多くの遺体がここで火葬されるようになりました。八宝山で火葬された市民の多くは、なだらかな丘の上に建つ納骨堂「老山骨灰堂」を利用。故人の写真をはめこんだ木箱に遺骨を納め、ここの棚に安置します。

さらに、多様化する葬送
さて、数千年も延々と続いた土葬から、簡素な火葬へ。そして、近年では、揚子江河口での撒骨も盛んになりつつあるなど、葬送スタイルの多様化が進んでいる中国。しかし、どんなにスタイルが変わっても、人々の死者への思い、祖先への思いは変わらないのではないでしょうか。心の奥底に変わらぬ思いを抱きつつ、経済の発展期を迎えた時代にしなやかに順応していく。新しい葬送のスタイルから、中国の人々のたくましい姿が見えるようです。

インドネシア
インドネシア・トラジャ族の壮大なお葬式
日本人の心の故郷を垣間見せてくれる貴重な文化遺産
儀礼が三年に及ぶことも
インドネシアの東部、スラウェシ島(旧セレベス島)の中部高地に住むトラジャ族の葬儀は、その規模と期間の長さからいって、世界でも他に類を見ないものです。また古代日本の葬送儀礼とも多くの共通点を持ち、興味がつきません。その大きな特徴は、死後に一定の期間、「もがり」の風習のあること。「もがり」とは、人が死んで葬られるまでの期間、故人の復活を願ってその遺体を布などで巻いたりお棺に納めて仮に安置することで、仏教が広まる前の日本でもこの風習があったことが知られています。
少し前まで沖縄で行われていた風葬の中にも「もがり」の名残がありました。トラジャでは、家族が故人と一定の期間同じ家の中で暮らし、故人のそばで寝ます。故人をまだ病人として扱い、その復活を願うためでその期間は一般的には三ヶ月ぐらいですが、中には三年にも及ぶこともあります。

神輿のようにヒトは人間になった
子どもたちが家に帰り、親族も集まると、はじめて故人の"死"が確定し、いよいよ葬儀が始まります。まず村人が家の前の露台の前に集合。
遺体は身内の人々の手で露台の上に乗せられ、そのあと、高床式の穀倉の下に安置されます。その際人々は、さながら日本の神輿のように威勢良く喚声をあげてお棺を上下左右にゆさぶります。神となって冥界に赴く故人の心を奮起させるためなのです。お棺が台の上に据えられると、女達は故人の遺体を取り巻いて大声で泣きます。やがて広場で男達が静かに哀悼の歌を歌い始めます。


小指あるいは手の先で互いにつながって 円形になり反時計まわりにゆっくりと動きながら、掛け合い、朗詠のリズムで歌いつづける
その後、遺体は数日または数カ月を経て公の葬儀場へ運ばれ、安置された遺体を囲んで多くの村人たちが哀悼の歌をささげます。
そして葬儀のクライマックスとしてトラジャ族の富の象徴である水牛が犠牲(いけにえ)にされ、その肉が振る舞われます。犠牲の水牛の数が多いほど、葬儀は立派なものとして称賛されるのです。

日本人の祖霊崇拝の原点として
こうして故人を送る葬送の儀礼が終わると遺体は墓地へと運ばれます。墓地は村を見下ろす山の岩壁をくり貫いて作られたトラジャ族特有の先祖代々の共同墓地で、そこには故人の生前の姿をかたどった人形がいくつも並んでいます。神になった故人はここから村人たちを見守ってくれていると信じられているのです。
こうして長い長いトラジャ族の葬送儀礼はやっと終わりを告げるのです。このトラジャ族の葬送儀礼は、アジアの稲作民族に共通の文化であったようです。
それが仏教文化の浸透や近年の近代化の進行の中で変容し、またあるところでは全く姿を消してしまったと思われます。しかし、それは手厚く葬ることで故人は祖霊となって一族や村を守る、というアジア稲作民族の独特の葬送文化の原点として、私たち日本人の中に、今も脈々と流れているのです。トラジャ族の葬送儀礼は、私たち日本人の心の故郷の原風景を垣間見せてくれるのではないでしょうか。

チベット
厳しい自然環境と調和するチベットの鳥葬
厳しい自然環境と調和するチベットの鳥葬
自然環境が違えば、人々の考え方も異なり、弔い方も違います。
今回は、鳥葬で知られるチベットの葬儀についてご紹介します。

鳥葬のほかにも、 さまざまな葬儀がある
どこまでも続く空と平原、ゆったりと草を食むヤク、そして信仰の篤い人々。"世界の屋根"と呼ばれるチベットは、平均高度が東部で約三千メートル、西部では約五千メートルにも及ぶ広大な高原地帯です。
そんなチベットの地に、いまも息づいているのが鳥葬。遺体を鳥に食べさせるもので、人々にとって最も一般的な葬儀です。
チベットにはその他にも葬儀の方法があり、伝染病で死んだ人や犯罪者は土葬に、貧しい人や幼児などは火葬に、高名な僧や貴族、学者は火葬に付されます。また、ダライ・ラマのようにミイラにして祀られる塔葬もあります。

タルチョ(祈祷旗)
魂が離れた肉体だからこそ
では、実際に鳥葬はどのように行われるのでしょう。
まず、遺体は住み慣れた家に安置され、僧侶の読経によって、魂が肉体から解き放たれます。興味深いのは、四十九日までの期間、決して人々が故人の名前を口にしないこと。
特に死後七日間はまだ魂が遺族の周りにいるので、せっかくこれから彼方へ渡り、次の生に転生しようとしているのに、その名前を呼んでしまっては、呼び戻すことになってしまうと考えるのです。

鳥葬は、一般的に、死後二、三日から一週間後に行われます。その前夜には、僧侶とともに遺族も夜を徹してお経を唱え、早朝、葬列が出発します。僧侶の人数は、普通十人くらい。多いと百人を超えることもあります。遺族は何万個もの灯明をあげ貧しい人々に施しをします。
魂が離れ、単なる肉の魂となった遺体は、鳥葬場に運ばれ、天葬師と呼ばれる遺体の処理をする人によって、分解されます。そして、大きな岩、鳥葬台の上に置かれ、聖なる鳥、ハゲタカによってついばまれるのです。

鳥とともに、高く舞い上がって
日本人から見るとやや残酷にも思える鳥葬も、もちろんチベットの人々にとっては実に自然なこと。魂のなくなった肉体を他の生物に布施し、鳥とともに空高く舞い上がり、天に還る。だからこそ、鳥葬は天葬と呼ばれ、遺体を扱う人を天葬師と言うのでしょう。
また、鳥葬はチベットの自然条件にも合っています。特に中央チベットから西チベットにかけては、樹木が乏しく、火葬にするための燃料が不足していますし、岩場や凍土も多いので、土葬にも向かないからです。
大きく、厳しく、そして美しい自然。そのなかで、日々暮らしているチベットの人々にとって、死とは何か、生とは何か。自然の一部である自らの肉体を生物への施し物とし、魂は再び生まれ変わると信じる。その大らかさ、潔さ。それは、どこかチベットの広大な風景とも似ているのかしれません。

アメリカ合衆国
アメリカ合衆国の巨大メモリアル・インダストリー
葬をクリエイトするフューネラル(葬儀)・ビジネス
アメリカの葬儀業界は今から三十年程前に、強い消費者運動の洗礼を受けたことで事業の近代化と社会的地位の向上が図られました。
消費者ニーズの多様化に伴い、アメリカのフューネラル・ビジネスは存命段階での顧客獲得から遺体の処置、葬儀、埋葬までのトータル産業を目指しています。

"葬"を科学し、遺族の混乱を和らげる
オハイオ州にあるシンシナティ葬儀科学大学は一八八二年エンバーミング学校として創立された由緒あるカレッジです。
エンバーミングとは遺体に対する消毒・防腐・復元・化粧の処置の総称で、アメリカでは一般的に行われています。アメリカで葬儀業を営むためには通常、葬儀 ディレクターの資格とエンバーマーの資格の両方が要求されますので、学ばなければならない領域は多岐にわたります。ですから、ここは「葬儀エンジニアの養 成学校」といっていいでしょう。

シンシナティ葬儀科学大学
以下のような講座が設けられています。
◆ 葬儀ディレクターとして必要とされる講座
葬儀史/葬儀マネジメント/葬儀ディレクション/葬儀マーケティング/死生学/死の社会学/悲嘆の心理学/カウンセリング/プレニード/資金調達と価格決定/法学/他
◆ エンバーマーとして必要とされる講座
エンバーミング理論/解剖学/遺体修復技術/葬儀化学/病理学/細菌学/他

死や葬儀に関する専門書が収蔵されている。

学生はリアルな模型を用いることにより実践技術を体得する。
送る人、送られる人が心地よい、楽園空間での別れ
かつてアメリカで墓地といえば教会に付属した墓地を意味していましたが、今日では、葬儀業者の経営による新しい公園墓地が作られ、葬儀を教会で行うのは全体の5%程度になっています。最近の公園墓地には噴水や彫刻が並び、中には7千本ものバラの花が咲いているところもあります。また、葬儀は墓地内のフューネラル・ホームで行われます。フューネラル・ホームとは日本の斎場に近い施設で、チャペルや告別ホール、面談室、事務室、葬具展示室などが備わっています。フューネラル・ホームの式場室内には太陽の光、水、木の緑が取り入れられ、自然の中にたたずむかのような、開放的で心なごむ空間になっています。
愛情が合理的でクリエイティブな葬儀を生む
アメリカには香奠の習慣がありません。日本の互助会のようなシステムも存在しないので、生前に契約し自らの葬儀を準備する葬儀保険がビッグビジネスになっています。契約者は葬儀ディレクターと相談し、自分の葬儀の細部、花やドレスに至るまでを決めます。
アメリカ葬儀産業の様々なシステムには単に合理的という言葉だけでは片づけられないものがあります。その根底にある、葬儀を明るく前向きに受け止めようとする意志、そして故人を想う心や、残された者を想う心ゆえに、葬儀を納得いくまでデザインしようとする意識には学ぶべき点も多いのではないでしょうか。

イギリス
自然と共にあるイギリスの生と死
長い歴史を持ち、伝統と格式を重んじながらも、時に伝統の枠を打ち破る斬新な文化を生み出してきた国、イギリス。
そこに住む人々は、死をどのように考え、どのように人生の終幕を迎えるのか。今回は、イギリスの葬儀についてご紹介します。

老後は、自然に囲まれて
林や草原のなかをどこまでも歩いてゆける散歩道、優美なバラや緑のオブジェが美しいガーデン、そして窓辺を飾る可憐な花々。イギリスを旅するとき、私たちの目を楽しませてくれるのは、季節によってその色合いを微妙に変化させる自然の風景とすみずみまで手入れが行き届いた邸宅のガーデンです。
イギリスは、環境保護の団体「ザ・ナショナル・トラスト」の運動が盛んな地であり、かつガーデニングの本場。
いまは都会に住む人々の多くも、引退後は田園に移り住み、日々、緑のなかを散歩したり、読書をしたり、庭の手入れをしたり・・・。そんなゆったりとした生活をしたいと願っているといわれます。自然を愛し、植物に対して豊かな知識と技法を培ってきたイギリスの人々。彼らは人生のラスト・シーンを、どのように迎えるのでしょう。

簡素に、しかし厳かに進む葬儀
イギリスでは、どちらかと言うと、ごく親しい少人数の葬儀が中心です。それは、死はあくまでもプライベートなことであり、愛する者を失った悲しみは各人が心の中で噛みしめるものであるという考え方が、伝統的にあるからだとも言われています。実際、親しい友人や知人が亡くなったとの知らせを受けても、日本のお通夜のように、遺族のもとに駆け付けることはほとんどありません。 哀悼の気持ちは、それぞれが花束を贈ることで表現します。
葬儀は、死後、数日から10日ほど経った頃、火葬場に併設されたチャペルや教会、または故人が信仰した宗教の寺院などで執り行われます。式では、まず列席者一同でお祈りをし、賛美歌を歌います。そして、牧師が聖書を引用して故人の徳を讃えた後は、遺族や友人たちによるスピーチ。故人のありし日の姿をしんみりと、時にはユーモアを交えて語ります。そして、再び賛美歌とお祈りがあり、約三十分から四十分ほどの式は幕を閉じます。
このような簡素な葬儀のなかで、イギリスらしいものと言えば、霊柩車。近頃では、一般的な車両にまざって、葬儀用に特別に調教された黒馬が引く伝統的な馬車が人気を集め、復活を果たしつつあります。


花や木に、悲しみを託して
イギリスでは、現在、亡くなる人の約七割が火葬に、そして約三割が土中に埋葬されています。しかし、火葬と言っても、日本ように遺骨として形を残すものではなく、完全に燃焼させ、粉末状の遺灰とするもの。遺族が引き取った遺灰は故人の墓の周りやメモリアル・ガーデンと呼ばれる公園墓地、または故人の思い出の地や自宅の庭などにまかれます。

遺灰をまいたそれらの地にすでに植えられ、そして新たに植えられるのが、バラなどの花々や木々。そのため、墓地は自然が美しい公園のようにも見えます。
また、土葬の場合でも、埋葬した上に木を植える「green burinal(緑の埋葬)」が注目を集めています。生長する木によって、家族はいつまでも故人を思い出すことが出来ますし、豊かな緑ともなれば、次の世代の環境へも貢献出来るのです。さらに、棺も従来の木製に代わって段ボール紙などの素材を用い、環境に配慮するケースも登場してきました。
さて、愛する人が亡くなった後も、その人の眠る地で花を咲かせ、木を育てる。そして、故人に話し掛けるように植物たちに話し掛け、思いを馳せる。ラテンの国の人々と比べると、一般的に感情表現が控えめだと言われるイギリス人ですが、その姿には自然をこよなく愛する彼らならではの悲しみの癒し方があるように思えてなりません。

ドイツ
伝統と変革が混在するドイツの葬儀
ゲーテを、ハイネを、グリム兄弟を生んだ文化の国、ドイツ。
そして、自動車産業をはじめとするさまざまな分野で世界をリードする、ドイツ。
今回は、そんなドイツの葬儀についてご紹介します。

教会の影響のもとに
悠々と大地を流れる父なる河、ライン。そのほとりに点在する美しい古城と中世の面影を残す街並み。ヨーロッパのほぼ中央に位置するドイツは、さまざまな歴史に揺れ続けてきた国です。
この地に住む人々の多くはキリスト教徒で、カトリックとプロテスタントがほぼ半数ずつ。かつて教会は埋葬に対しても権限を持ち、原則的に教会がそれを執り行っていました。 カトリックではキリストが土葬されたと言い伝えられているため、当時、すべての信者はそれに準じなければならず、異教徒のものである火葬は固く禁じられていました。
十八世紀後半に、政府は葬儀に対する権限を教会から取り上げましたが、カトリック教会はいまも火葬を指示していません。そのため、今日でも、ドイツ全土での火葬の率は40%以下。最も一般的な葬儀の方法が、土葬なのです。


美しい花々を飾られて、鐘の音に送られて
では、ドイツの土葬はどのように行われるのでしょう。まず、遺体が納められる棺は一般的に木製で、黒や褐色の八角形舟形。内側には、シルクや紙などで作られたシーツが敷いてあります。棺は花で飾られ、月桂樹を施したスタンドに支えられます。死亡の通知は地方新聞に広告を出すのが普通で、友人や知人は訃報を知ると、遺族に花輪やカードを贈ります。

また、印象的なのが葬列です。都市部では条例により廃止されていますが、地方では、いまも昔ながらのおごそかな葬列を繰り広げることがあります。黒の喪服やシルクハットを身にまとった遺族や会葬者が、黒い布を垂れかけた馬車の霊柩車や棺持ちの手によって運ばれる柩の後ろをしずしずと歩を進め、墓地まで行くのです。ときには、先頭にブラスバンドが立ち、葬送曲を演奏することも。教会は、葬列が続く間、鐘の音を打ち鳴らし、死者への尊敬の念と参列者への感謝を示します。
墓地では、埋葬式が行われた後、まず司祭者が棺の上に土を三回かけ、遺族がそれに続きます。穴を埋めた後は、棺の形に土を盛り上げておき、遺族は好きな時にその小さな山の上や横に花やツタを植えるのです。
増えつつある火葬
このようなカトリックの伝統的な土葬がいまも続けられている一方で、火葬への動きも見逃せません。十八世紀後半には、すでに公衆衛生上の理由などで火葬が多く行われ始めましたし、十九世紀には、長い月日をかけて身体が朽ちていく土葬よりも、燃え上がる炎のなかで短時間に遺体が燃えていく火葬を高く評価しようという考え方が、知識層を中心に広がりました。現在では、ほとんどの墓地は火葬場を設置。

火葬は、人々や社会に対する教会の影響力が低下するにつれて、確実に普及してきたのです。
中世と近代、メルヘンの世界と最先端のテクノロジー、そして人々の生真面目な姿勢と陽気な笑顔。ひとつの国や国民にさまざまな素顔があるように、ドイツの葬儀の流れにも伝統と変革が混じり合い、これからも動き続けていくのでしょう。

フランス
自由と平和の国フランス・パリの埋葬
美しい街並み、貴重な絵画の数々、通りを闊歩する女性たちのファッション、グルメたちを惹き付ける美味、そして何より町にあふれる自由な雰囲気。訪れたすべての人を魅了する都市、フランス・パリ。
その都を愛し、そこで生を終えた人々は、どのように死後の世界へと旅立っていくのか。
今回は、フランス、特にパリの葬儀とお墓について、ご紹介します。

芸術散歩が楽しめるパリの墓地
パリでのんびりとした時間を過ごしたいなら、墓地へ行くといいという話をよく聞きます。実際、パリの墓地は、日本のお墓のイメージとはかなり異なるもの。ジメジメとした雰囲気はなく、明るく、まるで公園のようです。墓石も、華麗な彫刻を施したものや胸像のあるものなど、個性豊か。生前のその人の人柄や生き方を、ひとつひとつのお墓が語っているかのようです。
現在、パリには、二十カ所の市営墓地があり、そのなかの十四墓地は市内の交通の便のよいところにあります。いずれの墓地でも、一区画はすべて一メートル ×二メートル。お金持ちも、有名人もあらゆる人が同じ広さです。使用期限は六年から永代まで五タイプに分かれ、使用期限の過ぎたお墓は掘り起こされて次の死者のお墓へと変えられます。
各墓地には、フランス文花を花開かせた文学や芸術の担い手たちが多数眠っています。たとえば、パリ最大の規模を誇るペール・ラシェーズ墓地には、作曲家のショパンやロッシーニ、作家のドーデやプルースト、画家のモジリアニやドラクロワ、詩人のアポリネール、俳優のイヴ・モンタンなど、多彩な分野の著名人のお墓があります。
パリの貧しい家で生まれ育ち、後に愛の喜びや哀しみを歌って世界中の人々の心をとらえたエディット・ピアフも、ファンが捧げる美しい花々に囲まれてここに眠っています。

死後の復活を願って
また、ちょっと風変わりな観光スポットとして人気のあるのが、カタコンブと呼ばれる地下墓地です。ここは、ローマ時代の採石場の後で、無縁仏六百万体が納骨されているところ。複雑に入り組んだ暗くて広大な地下道の壁の両側には、たくさんの頭蓋骨が整然と重なって置かれ、ときには骨で模様まで描かれています。カタコンブは、第二次世界大戦の際、ナチスに抵抗したレジスタンスたちが、指令部を置いた事でも知られています。
頭蓋骨がこのように残っていることでも明らかなように、遺体は土中に埋葬され、一定の時間が過ぎると掘り返し、納骨されていました。いまでは、故人や遺族の希望で火葬にされることもありますが、多くの人々はやはり一般的な土葬を望みます。
というのも、フランス人の多くはもともとカトリック信者。キリストが十字架にかけられ、埋葬されてから復活したように、自らも復活を遂げ、永遠の生を受けるためには、遺体を消滅させてはならない、灰となってはならない、との思いがあるからです。実際、十九世紀以前には、「火葬せよとの遺言はこれを執行してはならない」との教会法があったように、カトリック教徒にとって、火葬は背信的な意味を持っていたのです。

安い料金で、誰もがあの世へと旅立つ
この国の葬儀もまた、多くはカトリックの教えに準じたもの。舟形の棺には、故人が成人であれば黒、子供であれば白の布を掛け、故人のイニシャルのついた盾を乗せます。葬儀の場には、黒のカーテンを張りめぐらし、棺とともに燭台を置きます。パリでは、葬儀の場の飾り付けをはじめ、遺体の搬送や納棺、葬儀用品の仕入れなどの基本部分を区営の公社が運営しています。また、葬儀の進行などを市営の葬儀社に依頼するとしても、その料金やサービスに関しては、厳密な規定があります。

そのため、掛かる費用は日本と比べてずっと安価。葬儀は福祉の一貫であり、社会全体でケアするものとの考えが根底にあるのでしょう。
誰もが安い料金で葬儀を行え、有名人であろうが、庶民であろうが、同じ二平方メートルの広さの土の下で眠ることが出来るパリ。そして、ある者は華やかな墓石を、ある者はシンプルな墓石を、またある者は芸術的な墓石を建て個性を発揮するパリ。それは自由と平等の国、フランスの都に生きる人たちにふさわしいフィナーレなのかもしれません。
エジプト
古代エジプト時代の死生観を受け継ぐエジプトのお墓
悠久の流れ、ナイル。
その大河の恵みに育まれ、数千年にも及ぶ高度な文明を誇ってきたエジプト。
今回は、そんなエジプトに焦点を当て、その地に住む人々の死生観や葬儀、お墓についてご紹介します。


死者が住む町
エジプト・カイロの郊外に、不思議な町があります。大小さまざまな家が立ち並び、道も縦横に走っていますが、人影はほとんどなし。実は、ここはいわゆる「死者の町」だからです。家に見えるのは大小さまざまな廟で、内部は生きている人間が住む家と同じように、居間やキッチン、洗面所まで揃ったものもあります。
エジプトに住む人々のほとんどは敬けんなイスラム教徒で、日々の生活は厳しい戒律によって定められています。メッカの方向に向けての一日五回の礼拝は欠かせませんし、断食のときには飲食はもちろん、唾さえ飲み込むことを禁じられているのです。
そんなイスラムの教えでは、葬儀や墓は質素でなければならないはず。実際、多くのイスラム教徒は、教えに従い、遺体を布でくるみ、棺に納め、簡素な墓に埋葬するだけ。
ところが、一部の資産家たちとはいえ、「死者の町」に見るような豪華な墓を建てるのはなぜか。それは、古代エジプト時代から彼らが受け継いでいる死後の世界への思いがあるからだと言われています。

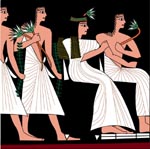
ガイドブック片手に、死後の世界へ
では、一体、古代エジプトの人々はどんな死生観を持っていたのでしょう。
まず、古代エジプトとは、紀元前約三千年から紀元前約三百年まで、およそ三千年続いた時代のこと。人々は多神教を信じ、現人神であるファラオ、すなわち王が社会の頂点に 立っていました。
古代エジプトの人々にとって、人生で最も大切なことは、再生復活。すなわち、死んだらあの世で生き返り、永遠の生を受けること。この世では悪いことをしないで過ごし、生まれ返ったあの世ですべての欲望を満たしたいと願ったのです。当時、ミイラづくりが盛んだったのもそのため。肉体の形を残しておけば、魂がそこに戻って宿り、死して後もこの世の人たちに会えると思われていたからです。
ミイラの包帯のなかには、「死者の書」といわれるものも入れられました。これは、死後に迎えるであろうさまざまな障害や審判を乗り越えて、無事、楽園に到達するための書。あの世へ入るための手順を記したガイドブックのようなものです。
死後の世界を信じた彼らは、社会的な地位に応じた規模で、死者のための家を建てたり、墓のなかに生前使っていた家具や化粧道具、玩具、楽器などの生活用品を入れたりしました。また、永遠に生き続けるためには、食料や飲み物も必要とされ、肉やパン、ワインなどの実際の食べ物を供えたほか、墓の壁に食べ物をうず高く積んだレリーフを描き、呪文によって死者が食べられるようにと取り計らいました。

死は、新たな出発
このように死後の世界を重んじた古代エジプト人によって次々と作られた「死者の家」やミイラ、豪華な副葬品の数々は、数千年の歴史を経た今、私たちをロマンの世界へと誘っています。しかし、実は、死後の世界を信じている点では、現代のエジプト人たちも同じ。イスラム教では、死は終着点ではなく新たな始まりであり、神アラーの審判の日に、死者は再び甦ると思われているからです。
さて、遺体を葬った土の上に石を積むだけの簡素な墓から、別荘のような墓まで、エジプトの墓はさまざまですが、死後の世界へ向ける人々の気持ちは同じ。ひとときは、愛する人と別れたとしても、いずれ再び会える。楽園では、何不自由なく幸せに暮らせる。そんな思いが、エジプトの地で出会う人々のとびきりの明るさや楽観性とも繋がっているのかもしれません。

どんな些細な疑問でもご相談ください。
無料相談
お問合せ・資料請求